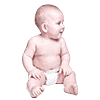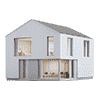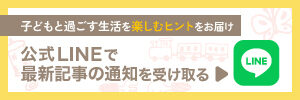赤ちゃんが生まれて100日頃に行う「お食い初め」。古くから受け継がれてきた大切な儀式です。せっかくお食い初めをするなら正しいやり方を知っておきたいですよね。そこでお食い初めについて順番・食べさせる人・必要なもの・服装などについて解説します。
お食い初めとは?いつ誰とするもの?

お食い初めとは?
お食い初めは、赤ちゃんに食べ物を初めて食べさせる真似をする儀式です。平安時代の宮中儀式として始まったといわれ、「一生食べ物に困らないように」という願いを込めてお祝い膳を用意し祝い箸を使って赤ちゃんの口元に食べ物を運びます。
いつ誰とするもの?
お食い初めは生後100日前後に行うのが一般的です。ただ地域によっては110日目、120日目などに行うところもありますのでぴったり100日目にこだわらなくてもよいでしょう。
100日を過ぎた後の土日や大安吉日に行うことが多いようです。お宮参りと同じ日にお食い初めを行う方もいます。
赤ちゃんの体調に配慮したり、パパとママの都合を考えたりして無理のない日程を選びたいですね。
以前は親戚や親しい知人を招待する方も多かったですが、最近ではパパママや祖父母など家族だけでお食い初めを行う方が増えているようです。お食い初めのやり方の形式にこだわりすぎずに赤ちゃんをお祝いする気持ちを大切にしたいですね。
お食い初めのやり方【家編】

お食い初めは家で行う方もいればホテルやレストランで行う方もいます。
家で行うメリットは赤ちゃんが環境に慣れていること、授乳やお昼寝がすぐにできることが挙げられます。また部屋を飾りつけたり、ゆっくり写真を撮ったりなど自分たちのペースで進められるという良さもありますね。
家でのお食い初めのやり方と必要なものにはどんな意味があるのかを詳しく見てみましょう。
必要なもの
お食い初めのメニュー
お食い初めのメニューは「一汁三菜」が基本で、それぞれの料理に長寿や健康への願いがこめられています。
・赤飯
古くから赤い色は邪気祓いや魔除けになるといわれているため、お食い初めでも赤飯が用意されます。赤ちゃんが病気や災難に遭わず健やかに成長するようにという願いが込められています。
・吸い物
吸う力が強くなるようにという意味があります。また、お食い初めの吸い物の具には蛤が使われることが多いです。それは蛤は対になっている貝殻以外とは合わないため、蛤の一対の貝殻のように良縁に恵まれて幸せになってほしいという願いが込められているからです。
・煮物
季節や地域にもよりますが、人参と大根でおめでたい紅白を表すことが多いようです。また穴があいていることから明るい先行きを表す蓮根、「よろこぶ」にかけて昆布、まっすぐにすくすくと成長するようにと筍を入れることもあります。
また、お食い初めのやり方として煮物を飾り切りにするとお祝い膳の見映えがよくなるということがあります。カボチャや椎茸を長寿の願いを込めて亀の甲羅に見立てて六角形に切ったり、人参や蓮根を見た目が華やかな花形に切ったりすると素敵ですね。
・香の物
香の物(漬物)には長寿の意味があり、口の中をさっぱりさせる役割もあります。香の物の代わりに、なますなどの酢の物を使う場合もあります。紅白なますにすると縁起がよくて彩りもきれいになりますね。たこの酢の物も「多幸」にかけて縁起が良いとされています。
・尾頭付きの魚
頭から尻尾まで1匹丸ごとで「首尾一貫(初めから終わりまで全うする)」という意味があり、長寿への願いが込められています。おめでたい(鯛)の語呂合わせや、赤い色がおめでたいことから鯛が使われる場合が多いですが、地域によっても変わります。
家で料理を準備するのは大変そうに感じるかもしれませんが、最近では冷蔵や冷凍で赤飯や鯛などがひと揃いになったお食い初めセットも販売されているので利用してみるのも良いですね。
お食い初め用の食器
お食い初めに使う食器はしきたりでは漆器の高足の御膳で、男の子が内外ともに朱色、女の子が外側が黒色、内側が朱色とされています。男の子が朱色、女の子が黒色と聞くと反対ではないかと思ってしまいますが、間違えて逆の色で用意しないように気をつけましょう。(※地域によっては男女の色が反対のところもあります)
また最近では正式な漆器でなくても、お食い初めの後もずっと使える幼児用の食器セットなども販売されているのでリーズナブルに用意することもできますね。
お食い初め用の祝い箸
お食い初め用の箸はお祝いの意味をこめて祝い箸を用意します。祝い箸は主に柳の木でつくられています。おめでたい席で箸が折れるのは縁起が悪いことなので水分が多くて折れにくい柳が使われます。
また柳は春に芽吹いて強い生命力があるために縁起が良く、薬木としても使われているので香りが良いという特長もあります。
箸の長さは縁起をかつぐ意味で末広がりの八寸(約24cm)で作られています。
祝い箸は必ず箸袋に入っています。祝い箸を包み清めて家族の幸せを願うという意味があるのです。市販でも美しい箸袋に入った祝い箸が多いですが、お食い初め用に可愛らしい箸袋を手作りする方もいます。
祝い箸の形には次のような種類があります。
・両口箸(りょうくちばし)
両口箸は、箸の両端が細く丸く削ってある箸です。これは一方が人が食べるため、もう一方が神様が食べるためという意味で、神人共食(しんじんきょうしょく)といいます。お祝い膳は神様にお供えしたお料理を神様と共に食すことで恩恵を授かるといわれています。
・俵箸(たわらばし)
箸の真ん中が膨らんでいて形が米俵のようなことから五穀豊穣の願いが込められています。子孫繁栄を表す意味で「はらみ箸」と呼ばれたり、また「太箸(たいばし)」と呼ばれたりすることもあります。
歯固めの石
お食い初めでは石のように丈夫な歯が生えることを願い小石を使って「歯固めの儀式」を行います。
正式には歯固めの石は黒、赤、白の3種類の石を使うとされていますが、なかなか見つからないことも多く現代ではあまりこだわられてはいないようです。地域によって違いもありますが、形の良い石を1つ用意すればよいでしょう。
では歯固めの石はどのように入手すればいいのでしょうか。
・お宮参りの際に神社から授かる
お宮参りのご祈祷の際に歯固めの石を授かることがあります。この場合は、歯固めの儀式に使った後はいただいた神社にお返しするのがマナーです。授かった際にお返しする時期が明記されていることもありますので確認してみてくださいね。お返しするときにはお礼参りも忘れないようにしましょう。
・河原などで拾う
河原などで気に入った形の石を拾い、儀式の前に煮沸消毒などをしてきれいにしてから使います。1~5cm程度で丸くてツヤツヤした小石が選ばれることが多いですが、パパとママが気に入った石を使うのが一番よいですね。できるだけ人に踏まれてなさそうなところから拾ってきます。
歯固めの石として使った後は元の場所に戻す方が多いようです。
・ネットショップなどで購入
専用に磨かれて形も整った歯固めの石がネットショップなどで販売されています。
購入した歯固めの石は儀式の後は記念品として家で保存しましょう。保存方法はよく洗った後に半紙で包んでおくのが一般的です。へその緒やお食い初めで使用した食器、記念写真などと一緒に保存しておけばよい記念になりますね。
また地域によってはお食い初めのやり方として、石の代わりに梅干しなどの代用品で歯固めの儀式を行うところもあります。代用品のそれぞれの意味は次のとおりです。
・梅干し
梅干しのようにシワシワになるまで長生きできますようにという意味があります。
・たこ
「多幸」という語呂合わせで縁起の良い食べ物とされています。また「硬いたこも噛み切れるような丈夫な歯が生えますように」「たこの吸盤のようなきれいな歯並びになりますように」などの説もあります。
歯固めとして使う時は赤ちゃんの口元に近づける時の安全のために吸盤は取り除いておきましょう。
・栗・くるみ
栗やくるみは硬い殻に覆われているため、硬いものも噛める丈夫な歯が生えてきますようにという願いが込められています。
・紅白餅
紅白は縁起が良いこと、また餅と「長持ちする」を掛けて長寿を表しています。
料理の並べ方

手前左・・・飯椀(赤飯やご飯もの)
手前右・・・汁椀(吸い物などの汁もの)
中央・・・高坏(歯固めの石、梅干しなど)
左奥・・・平椀(煮物など温かいもの)
右奥・・・つぼ椀(香の物、酢の物など冷たいもの)
お膳の外・・・平皿(尾頭付きの魚)
(※宗派などによって並べ方が異なることがあります)
お食い初めのやり方・順番
実際には赤ちゃんはまだ食べることができないので、口元に運んで食べさせる真似だけをします。儀式の後、お祝い膳の料理は家族で美味しくいただきましょう。
また、お食い初めの料理を食べる順番には正式な決まりがあります。近年はあまりこだわらない方も増えているようですが伝統的な順番は次のようになります。
・赤飯、吸い物、尾頭付きの魚のみの場合
赤飯→吸い物→赤飯→魚→赤飯→吸い物
の順に祝い箸で食べ物を赤ちゃんの口元へ持って行きます。
これを3回繰り返したら最後に歯固めの儀式を行います。
・上記に加えて副菜も食べさせる真似をする場合
赤飯→吸い物
→赤飯→魚→赤飯→吸い物
→赤飯→煮物→赤飯→吸い物
→赤飯→酢の物→赤飯→吸い物
→赤飯→歯固め→赤飯→吸い物→赤飯
(※地域によって順番が異なる場合もあります)
もし食べさせる真似の順番を間違えても問題はありませんので安心してください。赤ちゃんの成長を願う気持ちが一番大切ですので形式にとらわれすぎずに家族で楽しみながら行いましょう。
また途中で赤ちゃんが泣き出してしまった場合も一旦中断し、泣きやんでから再開するなど臨機応変に対応しましょう。
お食い初めのやり方・石を使った儀式
歯固めの石を直接赤ちゃんの歯茎にあてるのは誤飲や歯茎を傷つけてしまう恐れもあります。現代の歯固めの儀式は、まず歯固めの石にお箸を軽くあて、そのお箸を「石のように丈夫な歯が生えますように」という願いを込めながら赤ちゃんの歯茎にやさしくちょんちょんとあてる方法がとられています。
お食い初めに適した服装は?

赤ちゃんの服装
古来からお食い初めと同時に行われてきた儀式として「お色直し式」があります。お色直し式は、それまで白色の産着を着ていた赤ちゃんに母方の実家から贈られた色付きの小袖を初めて着せる儀式です。
最近は袴風のロンパースも販売されていますので手軽に和の雰囲気を出すことができます。ロンパースなら動きやすいので赤ちゃんも快適ですね。
また和装にこだわらなければ男の子ならタキシード風、女の子ならドレス風のロンパースでおしゃれするのもよいですね。蝶ネクタイやレースの付いたつけ襟風のスタイをつけるだけでも素敵ですよ。
パパとママの服装
ママはスーツやセミフォーマルなワンピース、家でお食い初めを行う場合は上品な雰囲気のスカートにブラウスでも大丈夫です。赤ちゃんが和装の場合、ママの負担にならなければ着物を着るのも統一感が出て素敵ですね。
パパはスーツを着る方が多いですが、ママの服装がそこまでかっちりしたものでなければシャツにチノパンなどでもよいでしょう。
祖父母の服装
せっかくのおめでたい日に体調を崩されることのないように季節や天候に合った服を選んで着てきてもらいましょう。
暑い日は涼しい素材の服にして冷房対策に羽織ものを用意、寒い日は暖かいインナーを着用して念のために防寒用のストールなども用意しておくのがオススメです。
また両家の祖父母が参加する場合は、当日、片方がフォーマルな装いで片方がカジュアルな装いだとお互い気まずい思いをしてしまいますよね。事前にパパとママが双方にどんな服装で来るのか確認しておきましょう。
お食い初めのやり方・祖父母を招待する場合、誰が食べさせる?

お食い初めで赤ちゃんに食べさせる真似をする人を「養い親」といいます。
長寿にあやかるという意味から出席者の中の最年長者が養い親を務めます。最近では祖父母に養い親をお願いすることが多いようです。お食い初めの儀式のやり方は男の子なら祖父、女の子なら祖母が養い親となり、赤ちゃんを膝の上に抱いて料理を食べさせる真似をします。
祖父母が出席しない場合はパパママがその役割を担い、お食い初めの儀式のやり方は祖父母の時と同じく男の子ならパパが、女の子ならママが食べさせる真似をします。
お食い初めのやり方は関東と関西で違う?

お食い初めのやり方は地域によって異なる場合があります。
例えば歯固めの儀式では、関東では歯固めの石が一般的ですが、関西ではたこを使うことがあります。
料理では関東では尾頭付きの魚は鯛を用意することが多いですが、関西ではホウボウという鯛と同じような赤い色をした魚を使うことがあります。「頭の骨が硬くなるように」「夜泣きをしないように」といった願いが込められているといわれています。
また、お食い初めの儀式の日程を先に伸ばすことで赤ちゃんが長生きできると考えられ、生後120日以降にお食い初めを行う地域もあります。
お食い初めで親は何を食べる?

赤ちゃん用の祝い膳は実際には赤ちゃんはまだ食べることはできないので儀式の後に大人が食べます。
追加で料理を用意するとしたら、見た目が豪華な寿司はおもてなしにぴったりでしょう。赤飯があるのでご飯ものはいらないという場合は刺身を盛り合わせにするとテーブルも華やかになりますね。
またスーパーやデパートなどでオススメの料理を組み合わせてくれるオードブルを注文しておけば様々な料理が盛られているので、出席者の食べ物の好き嫌いもあまり気にしなくて済みますね。
盛り合わせではなく出席者に個別に食事を用意した方が食べやすいという場合は、仕出し弁当やホテルの宅配弁当など少し高級なお弁当を人数分手配するという方法もあります。
お食い初めのやり方【お店編】

最近ではお食い初めをレストランやホテルでする方もいます。
お店でおこなうメリットは、まず準備や片付けの手間がなくパパやママの負担が少ないことです。
また、レストランやホテルなどのお食い初め専用プランなら家より高級感や特別感を出すことができるということもあるでしょう。
さらに、お食い初めに慣れている店員さんに進行手順を教えてもらったり、写真撮影を頼んだりできるということもあります。お食い初めの経験がないパパやママでも安心して行うことができますね。
お店でお食い初めを行う時はなるべく個室を予約しましょう。生後100日前後の赤ちゃんが慣れない環境で急に泣き出してしまうこともあるかもしれません。せっかくのハレの日なのに他のお客さんたちを気にしながらのお祝いになってしまうと大変ですよね。
また家から近いお店を選ぶことも大切です。家から遠い場所だと遠出に慣れていない赤ちゃんの負担になってしまう可能性があるからです。
人気のお店は歓送迎会シーズンや年末年始といった時期には予約が取りづらいものです。お食い初めをしたい時期が繁忙期と重なる場合、早めに予約するようにしましょう。
個室利用料や急な体調不良などの時のキャンセル料など心配なことは事前にWebサイトや電話で確認しておいた方がよいですね。洋室の場合は赤ちゃんを寝かせられる場所があるかも確認しておきましょう。
お食い初めは子どもを慈しむ心を大切に自分たち家族に合ったやり方で

お食い初めには古くから受け継がれてきたやり方も大事ですが、形式にこだわりすぎずに「子どもを慈しむ心」を大切にして自分たち家族に合ったやり方でお祝いしましょう。
アイフルホームでは「子育ても家事も暮らしも、もっと楽しくなる住まい」をテーマに『FAVO for KIDS』という住まいをご提案しています。大人数を呼ぶ行事やパーティにおすすめな「つながるダイニングキッチン」に興味を持たれましたら、こちらから詳細をご覧ください▼